|
|
|
|
|
|
|
フリクションプレートは 結婚する直前に3台分ほど買ってあった筈で これを発掘するところから始めた。 クラッチ滑りの原因はどうあれ 今回はノーマルフリクションプレートと バーネットのスプリングを入れて組むことにした からだ。 バーネットスプリングのクラッチの重さは聞きしに勝ると言われているので 気が乗らないが なんとか今回で ケリを付けたい一心からの決定だ。 フリクションプレートは 耳の部分に切り欠きのあるものが出てきた(現在注文すると これが出ると思う)ので これを使用することにした。 まずはクラッチ板をばらしたが…。 |
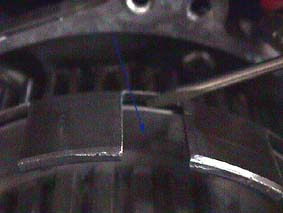
|
クラッチ板をすべて外した。 バーネットのフリクションプレートがオイルに漬け足らなくて焼き付いたのでは ないかという意見も有ったが オイルの独特の焦げ臭さもなく 一見して問題なさそう だった。 プレート類とスチールリングの数を番町皿屋敷のように数えた。 あれ?スチールプレートが一枚足らない。 もう一度数える。 やはり一枚足らないぞ〜。 ハウジング側を眺める。 な〜んだ ハブにくっついているじゃあないか〜。 写真は マジでドライバーで取ろうとしている図だ。 |

|
青矢印の部分は スチールプレートではなく ハブと一体になった部分だ! それによく見ると かみいさんが言っていた ハブ側の刻印らしきものもあるでは ないか! が〜ん これは後期のハブである! うお〜。 |

|
さて ここで分かりやすいように 資料写真を見てもらうと これは前期後期のハウジングの違いである。 左は前期型で 右の軽量化のための肉抜きが目立つ方が後期型である。 赤影は前期のハウジングが付いている。 |

|
次に問題のハブであるが 左は前期型で 一番奥には爪があり そこに アウタープレートと称する スチールプレートの径の小さい版みたなのんが1枚 入って その上にスチールプレートが付くようになっている。 それ以後は7枚ずつのスチール フリクション両プレートとスチールリングが入って スプリングプレートで蓋をするようになっている。 一方後期型は 奥の帽子のつばのようになっているところに直接フリクション プレートを入れるようになっていて スチールプレートが一枚少なくなっているのだ。 |

|
これは 前期型のスプリングプレートの裏。 ハブと嵌まる溝は切っていないので ハブに対してどの組み合わせで被せても 問題がない。 厚みは8ミリである。 |

|
これは実際にはH2のスプリングプレートであるが 後期プレートはこの様にハブと 噛み合う溝が彫ってあり マークが合うところで嵌めなければ ハブに入らないように なっている。 すなわち嵌まらなければ クラッチ板を押さえつけないのでクラッチが繋がらなくなるのだろう。 厚みは10ミリあり 前期型との差2ミリは その分ハブ側に入り込むように なっているそうだ。 前期型は ハブに対しばねで止まっているだけであったが 後期型は溝でハブに嵌まってよじれないように固定されるように 改良されたのだろう。 |

|
さて これで赤影には 前期型のスプリングプレートとハウジング そして後期型の ハブが使われていたことが分ると思う。 ではそれが何故に滑りやすい理由になっていたのか…。 まず前期型は 矢印の爪からハブ前縁までの長さが36.5ミリだった。 |

|
次にアウタープレートを入れると その長さがちょうど35ミリだ。 前期型はここから更に一枚スチールプレートを入れてからフリクションプレートを 入れるようになっている。 スチールプレートは約1.6ミリの厚みである。 一方後期型のツバから前縁までの長さは ちょうど35ミリであり この後プレートを 組むと 前期型よりもスチールプレート一枚分ゆとりが出ることになる。 本来後期のスプリングプレートを使うとその差はスプリングプレートがハブに 入り込むことで解消される筈であったが 前期型のプレートが使われていたので ばねの縮みが1.6ミリ弱かったのだろう。 |

|
このスチールプレートの厚み1.6ミリは ばねの機能を弱めるのに充分な厚み だったのかもしれない(なにせバネを0.5ミリ長く作って強化しようと考えるぐらい なのだ)。 ここでPOP南に相談したが つばのところに一枚スチールプレートを置くのは あのつばの部分の処理がスチールプレートよりも格段良いので もったいない とのことだった。 彼は バネの縮み1.6ミリ分を バーネットのスプリングで補えば 良いではないかという。 機械が補えなかった分は左手筋力を鍛えて補ったらシマイやと…。 ワハハ その通りかもね! |

|
バーネットスプリングはキンキラ金の 見るからにちゃっちそうな色をしている。 材質も硬いらしいが 少なくとも長さが全然違うのだ!。 この違いを見れば1.6ミリぐらいなんのこっちゃである。 |
|
しかし まさかそんな妙な組み合わせのクラッチが入っているとはつゆ知らずに 二度手間を踏んだものだ。 新品未使用と謳われていたのは一体なんだったのだろう。 はじめに手に入れた時にこんなことをチェックしていなかった自分も悪いのだろうが とんだ食わせ物である。 しかし 譲っていただいたお方をなじってはいけない。 取引は成立したとたんに個々人の責任であり それよりも気が付いていたとしても譲ってもらっていただろう。 それにこの組み合わせは彼が悪いのではないかもしれない。 メーカーから出荷された段階で この組み合わせであったのかもしれない。 むしろそのような可能性が高いような気がしている。 この一連は こんなこともあるのだなあという知識程度に流してもらって良いと思う。 |

|
バーネットバネは かなり長く フリクションプレートを留めるネジを入れるのにかなり 力が要る。 前にも書いたが 斜めに入ったりするので 写真のように長めのネジを用意して これで締めようかと思った。 |

|
しかし 全部締め込んでも 5ミリほど浮いてしまう。 これは奥の方はネジを切っていないからだ。 ネジを切ってあれば この長めのネジを入れたままでも良かったが…。 |

|
長めのネジを使うと 指でも締めることが出来るぐらい余裕である。 くれぐれも正しくスプリングプレートを締め込もう。 |

|
一度長いネジで仮に留めてしまってから 一本一本もとのネジで留めなおす。 これで安全に斜めにねじ込むこともなく作業することが出来た。 ネジ山をいためる可能性のあるド素人には良い手かもしれない。 くれぐれも斜めに入っていないか注意して欲しい。 それと柄の短いレンチでここを締めると 隣のネジや スプリングガイドの角で 指の第二関節を切るので注意(といってもやるだろうな)。 |

|
オイルストーンで軽く面出しし 油分を充分除去して組んだ。 しかし マフラーが付いたままでは 合わせ面の一番下面の漏れやすいところに オイルストーンを入れにくく 拭き取りもし難い。 不精は禁だ。 二回目は一回目に比べて かなり作業が早く進んだ。 何よりも原因がハッキリしたので 晴れ晴れした気持ちだ。 恐らくはバーネット板と0.5ミリオーバースプリングでも うまく行ったのかも しれないが バーネット板のオイルの汚れがひどいことから 純正の板を使うことにした。 |
次回 大団円